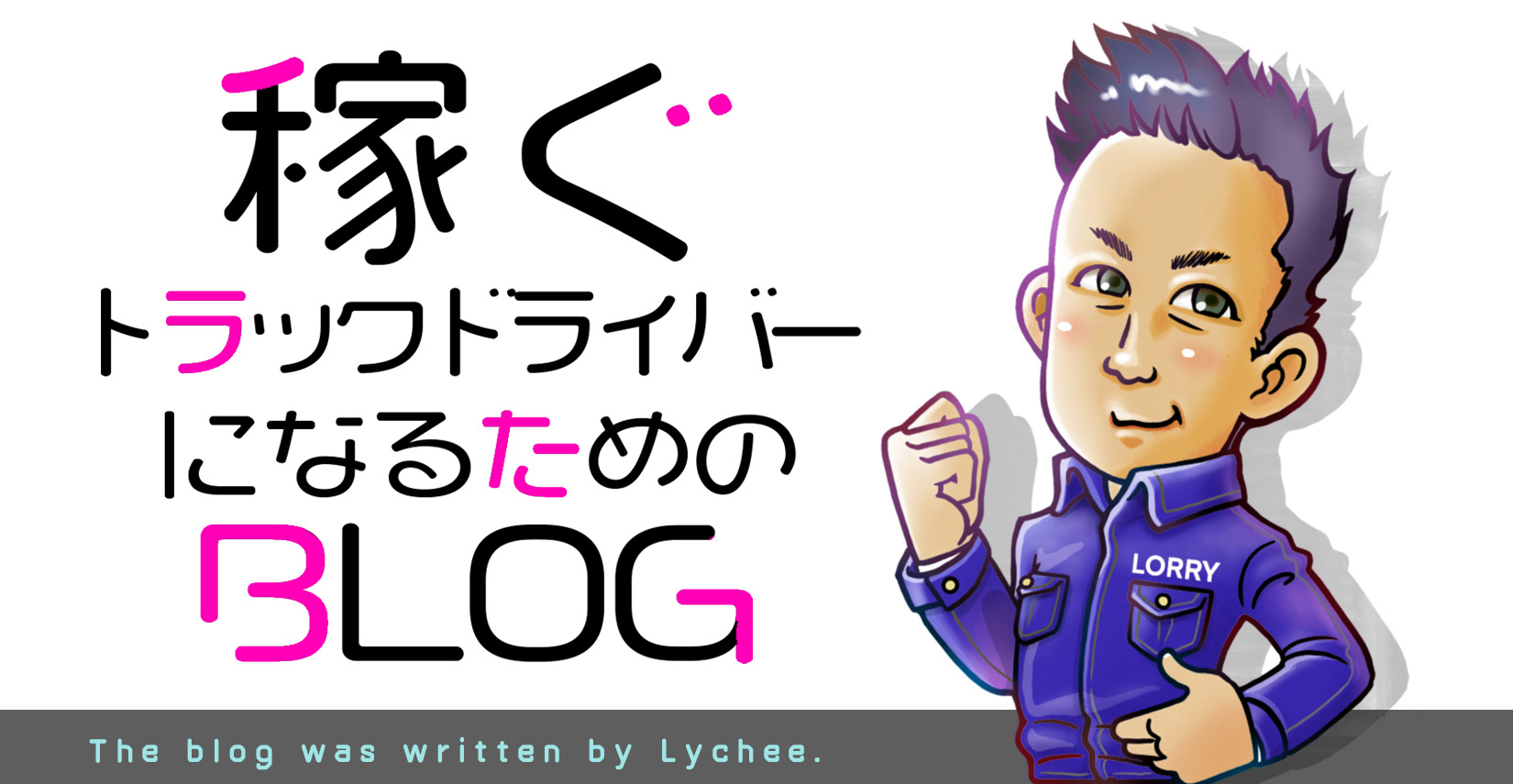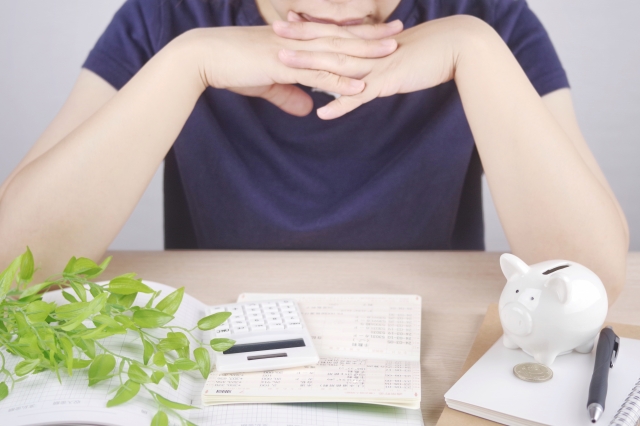トラックドライバーの私が中古の一棟アパートを購入したらどうなった?

今回は、トラックドライバーである私が中古の1棟アパートを購入し、資産拡大に挑戦したケースをもとに、不動産投資がどのように資産形成に影響するのか、また実際に購入した感想や課題について掘り下げていきます。
数年前、私はトラックドライバーとして日々働きながら、将来の安定を求めて資産形成をどうしていくのかを考えていました。

将来的に年金はあてにならないし、身体が資本の仕事をしているので、60歳や70歳まで元気に働ける保証もないので、本業とは別の収入源を作る必要をいつも感じていました
自己投資として書店で興味を引くタイトルの書籍を購入したり、トラックの運転中に投資系YouTuberのチャンネルをラジオ感覚で聴いて情報収集をしていくうちに、
- 株式投資(高配当投資、投資信託、デイトレード)
- 仮想通貨
- FX
- 副業(ブログ、アフィリエイト、せどり、動画編集、SNS発信、Webライターなど)
- 不動産投資
このような稼ぎ方で財産を築いている方の発信を参考にしました。
私はこのほとんどを実際に試してみましたが、デイトレードやFXは数百万円ほどの損失を抱えて断念…。
高い授業料を払って私が行き着いたのは、

なるべくギャンブル要素が少なく、再現性のある稼ぎ方でないとダメだということです
そして現在、私が続けられているのは、
- 株式投資(高配当株、投資信託)
- 副業(ブログ、アフィリエイト、せどり)
- 不動産投資
これらになります。
とりわけ資産拡大に大きく寄与したのは株式投資…ではなく実は不動産投資なんです。

現在はアパート、マンション、築古戸建てなど、数件の不動産物件を所有しており、家賃収入に家計が大きく助けられています
そこで今回は、トラックドライバーの私が数年前に最初の1棟アパートを購入し、資産拡大に挑戦したケースをもとに、不動産投資がどのように資産形成に影響するのか、また実際に購入した感想や課題について掘り下げてみます。
なぜトラックドライバーの私が不動産投資を選んだのか?

トラックドライバーという職業は、比較的に安定した収入を得られる仕事です。
一方で、体力勝負の部分が大きく、長期的に続けるには限界があると感じる人も多いのではないでしょうか。

トラックドライバーは自分に向いている職業だと思っていますし、現在は楽しく仕事をさせていただいているのですが、高齢ドライバーになると判断能力が低くなってきますし、残念ながらいつまでも続けられる仕事とは思ってなかったです
こうして私が不動産投資を検討した理由は以下のとおりです。
1. 収入源を多様化したい
トラックドライバーは頑張れば月収50万円以上を稼ぐことも可能ですが、収入源が「仕事」だけでは、やはりリスクが高いと感じます。
不動産収入があれば、労働収入に依存せず収入を安定させられると思いました。
2. 老後に備えたい
年金だけでは生活が厳しいと考える人が多い昨今、古くから行われてきたビジネスである不動産賃貸業で家賃収入を得られれば、老後の資金の不安を軽減することができると思いました。

地域貢献ができて、老後も取り組める事業として不動産賃貸業は良いと思いました
3. 資産形成と、できる範囲で節税もしたい
アパート購入は資産として残るだけでなく、経費計上による節税効果も期待できます。

日本の土地の価値は世界的に見ても安定しており、株式のように激しく乱高下することはありません
比較的に安定した資産になるので、将来的に子供に相続も考えられます
1棟アパート購入の具体的な流れ

本当に儲かる良い物件は1,000件のうち3件しかないとも言われる不動産投資。
私が物件価格が何千万円もする中古の1棟アパートを購入する際に、どのような手順を踏んだのか、簡単に説明します。
1. 情報の収集
- 不動産会社やインターネット(楽街や健美家、アットホームなどのポータルサイトを毎日チェック)を通じて、物件を探します。そして実際に何件も何十件も物件の内覧を申し込みます。そうして物件の良し悪しを直に見ることで、物件の「選球眼」を身に付けます。
- 不動産投資の実践者の書籍やブログ、YouTubeをチェックして、自分よりも先をいく先輩の失敗経験を学ぶ。勉強をすることで、初心者や誰もがハマりがちな失敗を回避できるのですから、そうなると勉強をしないことがリスクとも言えます。これは余計な損失を被らないために大事な考え方です。
- 「利回り」や「空室率」、「指し値」といった不動産投資をする上で欠かせない、基本的な指標を学び、収益性のある物件を見極める目を養います。

今にして思っても、情報収集はしすぎるくらいにしておいて良かったと思っています
不動産業界は騙し騙されがまかり通っている業界なので、自分を守れるようにしっかり知識武装をしないと高値掴みをさせられたり、あっさりと騙されることもあります。

仲介をしてくれる不動産会社の人でも、息を吐くように嘘をついてくることもあります(実体験)
新築ワンルームマンション投資の勧誘とか、あれに引っかかると一発で人生退場コースになる怖さがあるので、本当に気をつけなければいけません。
高収入な医者や弁護士といった職業の方は不動産投資において有利と思われがちで、それだけに営業を受ける機会がよくあると思いますが、知識武装をしていないと新築ワンルームマンション投資などの営業に簡単に引っかかったりして、最悪の場合は破産に至ることまで実際にあります。

とくに、営業マンの『節税にもなりますよー』という宣伝文句には注意が必要で、勉強をしていれば不動産投資は節税できるからという理由だけでやるものではないとわかるはずです
不動産投資において最大のリスクは、不動産投資の知識がないことです。
相場観が身についてなかったり、物件の適正な値段を自分で判断できないうちは知識が浅いので、不動産投資に手を出すにはまだ時期尚早と言えるでしょう。
実は、不動産の価格は『あってないようなもの』なんです。
それだけに正しい知識を持って自分が適正と思える価格で指値(いくらで買いたいか)をして、その値段で買えるかどうかが不動産投資で成功するためのカギになります。
2. 資金計画、融資審査の申し込み先を探す

物件を探す前に、自分が融資を受けられる金融機関を把握しておく方が良いでしょう
いざ良さそうな感じの物件を見つけたとしても、本当に良い物件だったらだいたい他にも何名かの買付け希望者がいたりします。
その中で最も優遇されるのは、現金での購入希望者になります。
確実に購入できるので当たり前ですよね。キャッシュは最強なんです。
次点では、仮審査をすでに通しており、融資を受ける目処がある程度ついている人が優先されます。
まだどこで融資を受けるかも決まっておらず、そもそも融資を受けられるのかもわからない人は競争になるとかなり不利になります。
競争に勝つ確率を上げるために、金融機関の目処は付けておく方が良いでしょう。

金融機関を探す上で注意点として、個人が不動産投資のために融資を受ける場合、三菱UFJ銀行などのメガバンクだとなかなか取り合ってもらえない場合が多いと思います
銀行によっては、個人のような規模の小さな案件には積極的になってくれない場合もあります。
不動産賃貸業のための融資を受けるためには、不動産賃貸業への理解があり、融資に前向きな銀行を探して審査申し込みをすることが近道になります。
- 三井住友トラストローン&ファイナンス
- 静岡銀行
- 滋賀銀行
- 関西みらい銀行
- 地元の信用金庫
- 日本政策金融公庫
など、融資実績のある銀行をネットで探して、自分が住んでいる地域に支店があるか?なども見て融資の申込先を選んでいきましょう。
- 金融機関からの融資を受けるためには、物件価格の1割〜3割ほどの頭金が必要になります。ただ今後規模を拡大していくことを考えるなら、できるだけフルローンで借りられる機関を探して、現金はなるべく温存しておく方が良いです。
- 公務員のように収入が安定していたり、継続して高収入を得ている弁護士や医師は「高属性の人」と呼ばれ、融資において優遇されやすいです。「高属性、中属性、低属性」といったランク分けで職業評価があるとすると、トラックドライバーは金融機関によっては「中属性」くらいの評価とされるかもしれません。ただ、私は真面目に数年勤務しており年収も安定していたのもあってなのか、金融機関からの融資はわりと普通に受けられたと思います。自分が収入の低い職業だとしても、例えば資産を多く持っていれば高属性と見なされる場合もあるので、どんな職業でも努力で銀行から高評価を得ることはできると思います。

2週間ほどの審査の後、銀行さんから、「融資大丈夫です」と電話で連絡をいただいたときは嬉しさと同時に、こんな私でも本当に何千万円も借りられるのか!と、少しびっくりしました
ちなみに私はマイホームの住宅ローンが残っていたのですが、不動産投資のための物件なら融資がおりるようです。
銀行の評価の見方としては、マイホームは何の収益も産みませんが立派な「資産」と見なされますし、賃貸物件は入居者からの家賃収入でローンを返済していけるからです。
実際に、住宅ローンの残債が1,600万円ほどあった私でも、3,500万円の融資がおりました。
銀行は、申込者の職業、年収、資産、返済能力、担保に入れられる物件の有無、購入物件の資産価値、CICの信用情報(過去に支払いの滞納履歴などがないか)などから、安心してお金を貸せる人かどうかを判断します。

ぶっちゃけ、不動産投資で規模を拡大していけるかどうかは、『金融機関から融資をどれだけ引けるかゲーム』といった感じで、自分の行動次第になります
年収が400万円〜500万円でも、立ち回り次第では数年で資産何億円にもなれるロマンがあります
3. 物件の選定
融資先の目処をつけたら、本格的に物件を選んでいきます。

- 無理なくローンを返済していける利回りか?
- 駅からの距離、築年数、周辺環境などを考慮
- 客付けができやすそうな地域か?
- 物件周辺にある競合物件の家賃や入居具合を調べる
これらを実際に現地を歩いたりもして調査しました
他には自分が管理できる地域、範囲内で探すのもポイントになります。
4. 物件の融資審査が通ったら契約と運用開始
- 無事に決済が完了すると契約完了。
- 物件の管理を管理会社に依頼するか、自分で管理を行うかを選びます。

本業のトラックドライバーの仕事をおろそかにしないためにも、物件の管理は管理会社にお任せする一択です!
自主管理にすると、物件に何か不具合があると24時間(夜中でも)電話対応しなければいけません。
- 入居者からの家賃の振り込み確認→一括で大家さんに振り込み。
- 滞納者がいたら支払いのお願い通知作業を代行。
- 退去者が出たら部屋の修繕作業→客付けのための広告手配。
- 物件に不具合が発生したら24時間コールセンターで対応。
- 万が一、孤独死などが発生した場合は部屋の様子を一番に確認に行ってくれる。
- 物件の清掃作業
家賃の5%ほどの管理料でこれだけの管理や客付けまでやってくれるなら安いくらいです。
購入後の感想:良かった点


私の一棟アパート購入後の感想をいくつか紹介します
1. 家賃収入の安定感を実感する

毎月の家賃収入があるのは、精神的に安心できる
これに尽きますね。
特に仕事が減った月でも家賃収入が補填になって、生活の安定感が増したことを実感します。
他には、インフルエンザで体調を悪くして家で寝込んでしまっている間も、家賃収入が稼いで家計を助けてくれた時などは特にありがたみを実感しました。
2. 資産が増えていくのを実感する
物件のローンを支払ううちに、資産が自分のものになる感覚を持てます。
時間とともにローンが減り、純資産が増えていきます。

不動産投資はレバレッジをかけた投資ですので、スピード感をもった複利の力で資産が増えていきます
不動産投資はレバレッジをかけた投資ではありますが、株の信用取引よりは全然負けにくい投資です。
もし物件が土地の値段に近い値段で買えたなら、最悪は土地値くらいで売却ができますので、ほとんど損をしない安心感があります。そこもメリットですね。
3. マネーリテラシーが向上
購入をきっかけに、不動産や税金、経済の知識をしっかりと勉強するようになり、結果としてお金の使い方に対する意識が変わりました。

勉強をするうちに、節税や資産の管理、今後の拡大を考えると会社を立ち上げた方がやり易いと判断したので、妻を社長にした株式会社を作りました
妻を社長にした理由は、妻はデザイナーの仕事をリモート勤務もしながらしており、週に2日は平日でも自由に動ける日があったからです。
金融機関は平日しか営業していないため、平日に動ける妻の方がやり取りがしやすかったためです。

私が全部やっていたときは金融機関との面談や、契約日のたびに有給休暇を取得しなければいけなかったので、妻が平日に動いてくれるようになって本当に助かり、感謝しています
購入後の課題:予想外の出来事


もちろん、アパート購入にはリスクや課題もつきものです
以下は、購入後に直面した代表的な問題です。
1. 空室問題
購入当初は満室だったものの、時間が経つと空室が増えることも。
管理の不備や、周辺環境の変化が原因となることもあります。
例えば、大学の近くで学生さんをメインの入居者としたアパートを持った場合、万が一にも大学が移転や撤退した場合は目もあてられない状況になります。
これは、少子化が進む日本各地で実際に起こっていることです。

私は商業施設など生活に便利な施設が近所に多数あるアパートを購入したので、比較的に客付け状況がよく、今のところほぼ満室状態を維持できています
一棟目の物件は、今後二棟目以降の購入や、規模拡大に繋げていけるかどうかに関わる重要な物件です。
それだけに、空室から何ヶ月も入居が決まらず、収益を得られないような物件を掴んでしまうと苦しい投資になってしまうので注意が必要です。
2. 突発的な修繕費
築年数の古い物件では、給排水管の故障や屋根の修繕など、大きな修理が必要になることもあります。これを想定して、収益の一部を修繕費用として確保するのが重要です。

「火災保険」は物件が火事になったとき以外でも、例えば台風で屋根が傷んだという場合でも保険がおりるので、うまくそういうのも使って修繕費を安く抑えられることも、知っておくと役立ちます
資産拡大への影響


私が1棟アパートを購入したことで、資産形成にどう影響を与えたのか、具体的に挙げていきます
1. レバレッジ効果
金融機関から融資を受けてローンを活用することで、少ない自己資金で大きな資産を持つことができました。
5,000万円の物件を購入するために自己資金500万円〜1,000万円を頭金に入れるイメージで、購入後は家賃収入からローンを返済しつつ資産を拡大できます。
例えば…
株式投資に500万円を投資すると、良くて年利7%で年間35万円の利益ですが、
その500万円を元に、5,000万円の不動産を購入して得られる年間収入は表面利回り10%の物件なら500万円になります。
1年で500万円を2倍近くにすることができるレバレッジ効果があります。
実際には、表面利回り10%としても実質利回り(税金や管理費を差し引いた利益)は約8%ほどになります。
このように、他人のお金を活用して、自分の資産を拡大する。
これは持たざる者が短期間で成り上がるためにできる有効な方法です。

このレバレッジ効果、持たざる者が早く資産を拡大させることができる方法としてはなかなかの破壊力ではないでしょうか?
2. 複利的な成長
家賃収入を再投資することで、不動産をさらに増やすことが可能です。
こうしたサイクルが長期的な資産形成に大きく寄与します。

不動産は一軒買ったら終わり…にはなりません
家賃収入の味を知ると、どうせ2軒目、3軒目と欲しくなってきます
毎月入ってくる家賃収入を次の物件を買うための資金にすることで、比較的に短期間で次の物件を購入することが可能になるんですよね。
不動産は、次々に拡大していけるロマンがあります。
かなり気が早い話ですが、規模の大きなメガ大家ともなると、毎年のように物件の購入を検討することになるので、資産を指数関数的に増やしていける可能性があります。
3. インフレ対策
インフレが進むとお金の価値は下がりますが、不動産の価値は基本的には上昇する傾向にあります。
これにより、長期的には資産価値を維持しやすいメリットがあります。

日本は今後は金利のある国になっていき、物価もますます上がっていくと思われます
何かしらでインフレ対策ができていないと家計は苦しくなっていく一方でしょうね
トラックドライバーの特性を活かした資産形成のコツ


トラックドライバーとしての特性を活かすと言いますか、トラックドライバーだからこそできる不動産投資をさらに効率的に進めるためのコツをいくつかご紹介します
1. 生活費の管理
長時間勤務のため、トラックドライバーは無駄な支出が少なくなりがち。
この特徴を活かして、家賃収入を再投資に回すことができます。

良い車を買ったり贅沢をしなければ、トラックドライバーは放っておいてもお金が貯まるハズです
贅沢をするのは、資産規模を大きくしてからにしましょう!
2. 地方物件への投資
トラックドライバーにとって、他県や遠方など、地方物件へのアクセスは有利と言えますね。
配送先でよく行く地域なら土地勘もできるので、広いエリアから物件を選択できるのは強みになります。
探すエリアの範囲が広いということは、掘り出し物件を見つけやすいというメリットがあるとも言えます。
銀行は、申し込み人が縁もゆかりもない他県や、遠くの地域の物件を購入するための融資を申し込んでくると基本的に渋るものです。
なぜその地域の物件を選んだのか?
物件に何かあったとき、どうするのか?
などの懸念要素があるためです。ですが物件を選んで購入する理由が、

『仕事でよく行く地域で馴染みがあり、土地勘もあるからです』というふうに堂々と説明ができるのがトラックドライバーならではの強みですね!
まとめ

いかがだったでしょうか。
不動産投資は安定した家賃収入が得られる一方で、空室や修繕といった課題にも直面します。
しかし、こうした経験を通じてマネーリテラシーが向上し、さらなる資産拡大に繋げていくことができると思います。

個人的に、トラックドライバーが不動産賃貸業を始めることは、資産形成の第一歩としてとても有効な手段だと思います
「資産形成に挑戦したい」「将来に備えたい」と考えているトラックドライバーの方は、不動産賃貸業を選択肢の一つに加えてみるのも良いかもしれません。
重要なのは、しっかりとした計画と知識を持ち、自分に合った投資を行うことです。

不動産投資は不労所得と思われがちですが、実はかなりバイタリティーが必要なビジネスです
行動力が必要なので、人によって向き不向きはあると思いますが、合う人は水を得た魚のように資産規模を拡大していける可能性があります
世の中には様々な投資法やビジネスが存在します。
中には一度の失敗で人生取り返しがつかなくなってしまうレベルの借金を背負ってしまうこともあります。
しかし、ちゃんと勉強をして知識を持って始めれば意外と損をしにくい投資として、私は不動産投資をオススメしたいと思います。
ではまたっ、ピース!